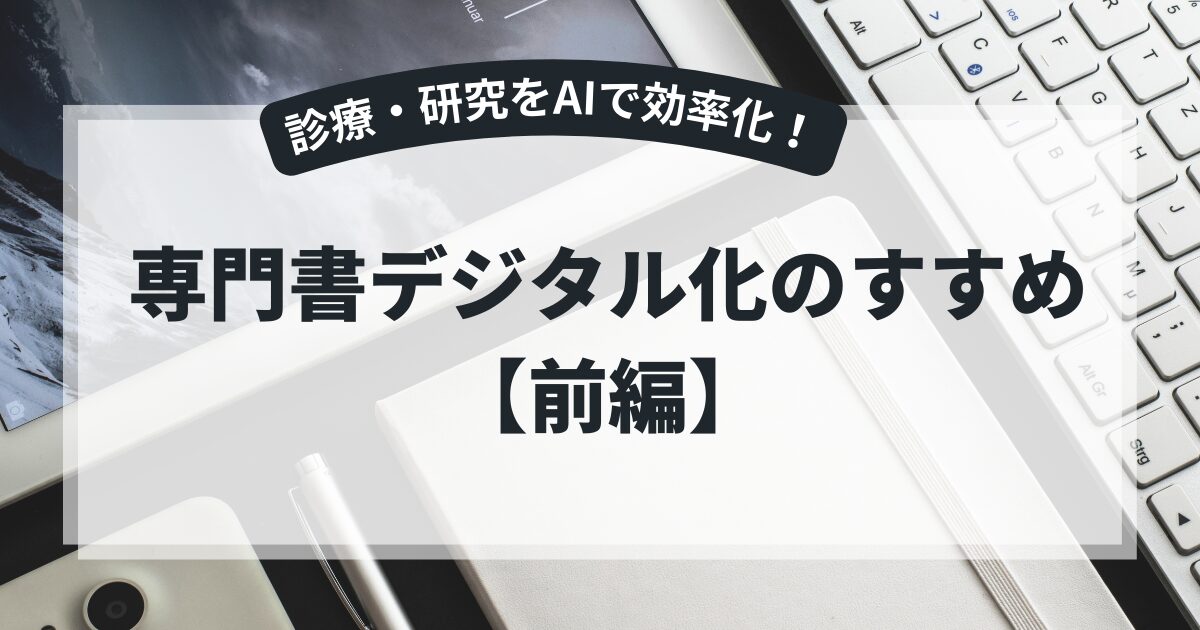臨床や研究の現場で「すぐに調べたい!」と思ったとき、分厚い専門書を棚から探し出し、目的のページを開くのは意外と大変ですよね。しかも急いでいるときほど見つからないものです。
獣医師に限らず、医師・薬剤師・看護師・研究者など、多くの専門職の方が同じ課題を抱えています。
そこで役立つのが、紙の専門書をデジタル化して、AIに“相談できる形”で活用する方法です。
この記事シリーズでは筆者が実際に試行錯誤して編み出した、「紙 → スキャン → OCR → AI活用」という流れを、前編・中編・後編に分けて解説していきます。
 にゃーす
にゃーす他に効率的な方法やアドバイスがあったらぜひ教えてくださいね
注意事項
まず、著作権に関する注意事項です。
- デジタル化した資料やそれらを読み込ませたAI(GPTsやNotebookLMなど)は、他人に使用させたり、公開してはいけません。著作権侵害に当たりますので、あくまで個人利用に留めてください。
- AIの答えを100%鵜吞みにしないようにしましょう。OCRの文字認識精度や専門分野におけるAIの認識・思考能力はまだ発展途上です。



私は、AIを「気軽に相談できる優秀な同僚」のイメージで使用しています
なぜデジタル化が役立つのか


まず、専門書をデジタル化するとどのような点が助かるのか、考えてみましょう。
紙の専門書あるある
獣医学の専門書は内容が濃い反面、1冊のボリュームもかなりのもの。狭い診察室に置いておくには適していません。
診察中に「あれ、この症状ってどんな鑑別診断があったっけ?」と本を開いても、目次や索引から該当箇所を探すだけで数分かかることもあります。
また、獣医療は日進月歩。新しい知見に合わせて専門書の内容も次々と改定されるため、本棚には新版・旧版が入り交じる状態に。
デジタル化のメリット
最近では、動物病院のカルテも電子化されているところが多いです。電子化により診療効率が格段にアップするのは誰しも異論がないところでしょう。
これと同じで、もし専門書やの内容がすべて検索可能なテキストデータになっていたらどうでしょう?
- タブレットやPCで必要な情報を一瞬で検索でき、診察を止めなくてすむ
- 情報や症状を入力し、AIにナビしてもらいながら診療をすすめる
- AIのサポートを受けながら、その場で診療プランを組み立てられる
- 複数の専門書や論文から関連する情報をまとめて提示してもらえる



診察の力強い味方になってくれるよ
OCR(光学文字認識)ってなに?
「紙の本をスキャンしただけ」では、ただの画像データに過ぎません。診察に活用できるようにするには、文字をAIに読み込ませる必要があります。
OCR(光学文字認識、Optical Character Recognition)は、その画像から文字を読み取り、検索可能なテキストに変換してくれる技術です。画像を読み込ませて文字データに変換するOCR専用のソフトもありますが、最近のスキャナーでは付属しているソフトにすでに組み込まれていることが多いです。



具体的な方法は、中編で説明します
まとめ


この記事では、紙の専門書をデジタル化することでどんなメリットがあるのかを、実際の臨床現場での使用例を交えながら紹介しました。
デジタル化をすることによって、以下のようなことが可能になります。
- 診察や研究での即時検索
- 複数文献の横断的な利用
- AIとの組み合わせによる診療プラン作成
ただし、OCRの精度やAIの限界、著作権といった注意点も忘れてはいけません。
専門書を「頼れる同僚」としてAIに組み込む第一歩は、まずスキャンと文字認識から始まります。次回の中編では、実際のスキャン方法やOCRを使った具体的な手順を紹介していきますので、ぜひ続けてご覧ください。