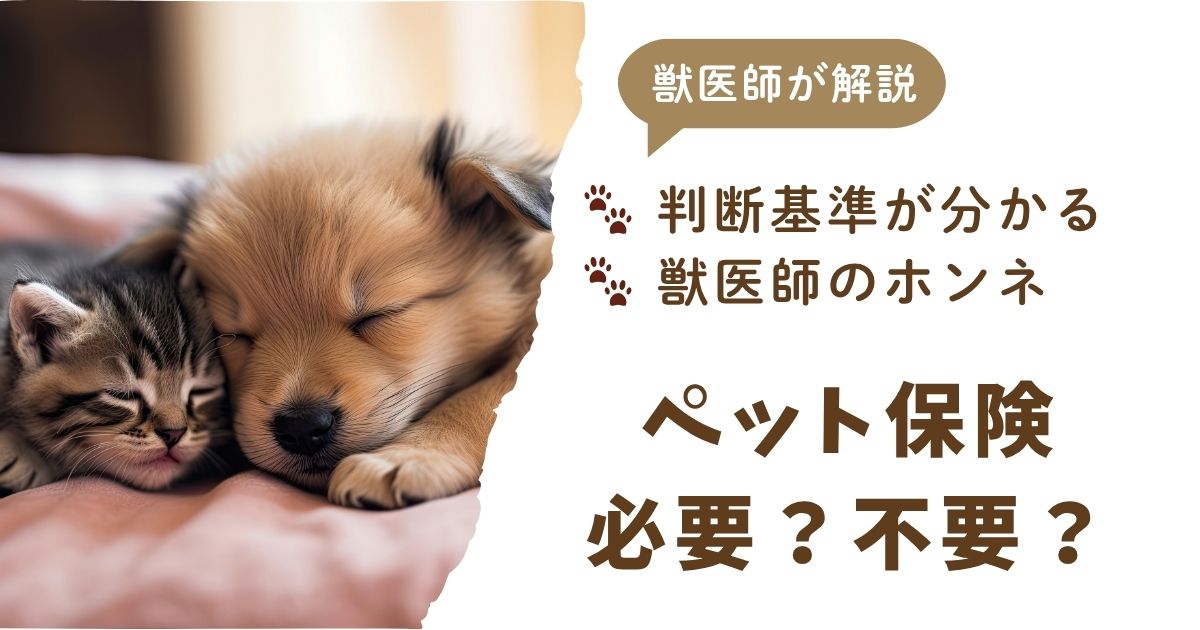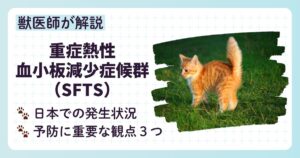「ペット保険って必要なの?」という声、飼い主さんからもよく聞きます。ネット上にも「必要派」「不要派」それぞれの意見があって迷ってしまいますよね。
 にゃーす
にゃーすペットの医療費は全て自己負担です
獣医師として日々の診療に携わる中で、保険の有無が治療の選択肢に関わる場面も見てきました。獣医療は日々進化しており、物価上昇や円安の影響も合わさって治療費が高額化しているのも事実です。
ペット保険はいる?いらない?


ペット保険は、ペットが病気やケガをしたときの医療費をカバーしてくれる民間の保険です。若いうちに加入すると保険料が安く持病などの制限も少ないのは、人の保険と似た仕組みです。
高額な治療費は突然発生することが多いです。
そのような時に「迷わずすぐ払える」なら問題ありません。しかし、「判断に迷いそう」「家族で意見が分かれそう」という場合は保険が「心のセーフティネット」になります。



まさに、「安心を買う」という考え方
ただし以下のような、予防目的の医療費は通常補償の対象外とされています。
- ワクチン
- 歯石取り
- 健康診断
- 望まない妊娠を防ぐための避妊、去勢術
不要派の意見①:ペットの治療費はそこまで高額にならない
一般的に、保険の基本的な考え方は「確率低、損失大」に備えるもの。火災保険や自動車保険を考えるとわかりやすいですね。
これに当てはめると「ペットの医療費は高いといっても、生活が破綻するほどではない」と考える飼い主さんもいます。
不要派の意見②:自分で備えればよい
月々の保険料を支払う代わりに積み立てなどをして備えておくという方法もあります。経済的に余裕があり、突発的な出費にも対応できる人には合理的な選択とも言えます。
現場獣医師が感じる保険のありがたさ


では、獣医師はペット保険をどのように考えているのかというと「保険に入っているとありがたい」というのが本音です。それは次のような理由です。
- 病気によっては治療費が高額になる
- 検査や治療の選択肢が広がる
- 費用のせいで諦める飼い主さんが減る
① 病気によっては治療費が高額になる
不要派の意見①で紹介した「ペットの医療費はそこまで高額にはならない」というのは、獣医師からするとそうとも言い切れません。
高額な医療費がかかる病気としては、「骨折」や「誤嚥」「尿路閉塞」「腫瘍(がんも含め)」などがあります。これらは、検査・手術・術後管理も含めると30万〜80万円が必要なこともあります。



急に用意するのは大きい金額
② 検査や治療の選択肢が広がる
保険に入っている飼い主さんであれば、費用を気にしすぎることなく治療方針を提案できます。最初から「最善の選択肢」を提示できるのは獣医師にとってもありがたいことです。



実は飼い主さんと同じくらい、獣医師も費用を気にしています
② 費用のせいで諦める飼い主さんが減る
近年は、物価上昇や円安の影響で治療費も上がってきており、輸入医薬品の価格は、去年より2倍ほどに上がっているものもあります。
もともとペットの医療は人の医療と比べてかなり割安で提供されていました。それは、獣医療関係者の努力や善意に支えられてきたものです。
今後は、企業が運営する動物病院の増加などにより、適正価格が高くなる流れもあります。
Q:ペット保険に入っていないと治療を断られることはある?
A:保険の加入状況によって獣医師から治療をお断りすることはありません。獣医師は保険の有無に関係なく、適切な検査や治療を提案し、その後の判断は飼い主さんに委ねます。
ただし、費用を理由に選択肢を制限せざるを得ない場面はあります。
保険に入る?入らない?判断のヒント


今までの流れを踏まえて、保険に入るべきかどうかのチェックポイントをまとめました。
- 家計状況から判断
- ペットの年齢・体質・性格から判断
- 保険の補償内容から判断
家計状況から判断
ペットの医療費は高額になる可能性もあり、それを保険で備えるのか、自分で備えるかは家庭の考え方や家計状況によって異なります。
「万が一の時にいくらまで出せるか?」を考えてみましょう。
ペットの年齢・体質・性格から判断
若いうちから慢性疾患を抱えている子や、やんちゃでケガをしやすい性格の子には、保険のメリットが大きいこともあります。
誤食や急性膵炎、胃腸炎など、健康に見える若い犬でも突然病気になることがあるため、早めに備えておくというのも1つの選択です。
Q.「保険は年を取ってから入ればいいのでは?」
確かに若いうちは大きな医療費がかかることは少ないです。
しかし、高齢になってからでは加入できる保険が限られてしまったり、保険料が割高になったりすることもあります。
保険の補償内容から判断
以下のようなポイントを確認してみましょう。
補償範囲
「通院は年○回まで」「免責金額あり」「治療費の○%を補償」など、保険の補償内容は会社によって大きく異なります。複数社を比較し、自分に必要な補償を精査してから決めましょう。



心配だからと、あれこれ掛けすぎないように
窓口清算
「窓口精算」とは、動物病院で診療を受けたときに、その場で保険が適用されて自己負担分だけを支払うという仕組みです。
窓口精算がない場合は、その場で飼い主さんが全額支払い、その後保険会社に補償分を請求という流れになります。
年齢による保険料の変化や更新の有無も大切
ペットの年齢が上がるごとに保険料が高くなる保険もあるため、契約前に確認しましょう。



長期的な目線で、無理なく続けられるかを考えましょう
持病があるペットの保険はどうしたらいい?


ペット保険は「持病は補償対象外」となることも多く、思ったほど保険が活用できないこともあります。
なぜ持病は補償対象外になるの?
保険は「将来起こるかもしれない不測の事態」に備える仕組みです。
多くの保険会社では、加入時に「過去○ヶ月以内に通院歴がありますか?」という告知があります。正直に書かないと「告知義務違反」となり、後日保険金の支払い拒否や契約解除の原因になります。
持病があるペットの医療費の備え方2つ
持病のある子は長期的に考えると医療費がかさみがち。どうしたらいいかというと以下の2つの方法があります。
- 持病があっても入れる保険に加入する
- 自分で備える
① 持病があっても入れる保険に加入する
すでに病気の診断を受けた子や、慢性的な症状がある子でも加入できる保険もあります。
ただし多くの場合、以下のような条件がつくことが多いです。
- 既往症(すでにある病気)は補償の対象外となり、その病気に関しては保険金が出ない
- 保険料が割高
- 補償内容や限度額に制限が付くことも(例:通院回数制限)
それでも、骨折や誤飲など「持病以外のリスクに備えたい」という飼い主さんには有効な選択肢です。
ポイントは「どこまで補償されるのか」をよく確認してから入ることです。



補償範囲が狭い分、保険料と内容が見合っているかを見極めましょう
保険には入らず自分で備える
もうひとつの選択肢は、保険には入らず医療費を自分で貯蓄するという方法です。
この方法のメリットは、自分でお金を管理しているため、持病も含めたあらゆる治療に使える点です。
一方で、お金の管理が難しかったり、短期間で病気やケガが重なる可能性もゼロではないというデメリットもあります。
獣医師の視点



持病がある子こそ「今後を見据えて」備えてほしいです。
たとえば心臓病の持病があるペットは、腎臓や肝臓にも影響が出てくることがあります。 持病のあるペットは保険で全部をカバーできなくても「ある程度の補償」か「備え」のどちらかがあれば、治療の幅は確実に広がります。
まとめ


保険の基本的な考え方は「確率低・損失大」に備えるもの。とはいえ、最近の経済の状況やペット医療の高度化で医療費も上がっている中では、獣医師にとっては保険に入っていてくれるとありがたいと思う場面もあります。
「うちの家庭、うちの子にとって最善の選択肢は何か?」をぜひ考えてみてください。