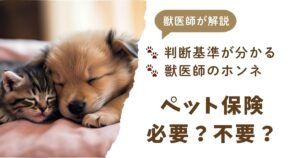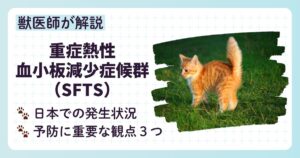犬や猫は一般的に7歳頃から「シニア期」といわれます。
ペットの7歳=人間換算で約44歳。そう聞くと「シニア」と呼ぶのは少し違和感がある方もいらっしゃるかもしれませんね。
実際、7歳になった途端に急に老け込むわけではありません。
シニアになるとかかりやすい病気も増えてくるため、7歳は健康管理に一層気を配り始めるとよいタイミングとも言えるでしょう。
この記事では、食事・生活環境・体調管理などシニア期を迎えたペットに必要なケア7選を獣医師の視点から解説します。また、飼い主さんの心や身体のサポート方法もお伝えします。
 にゃーす
にゃーす共に生きる時間を愛おしむ助けになったらうれしいです
シニア期のペットに必要なケアのポイント7選


老いてくると、体、心、行動に若い頃とは違った変化が見られます。シニア期のペットが快適に過ごせるようにサポートすべきポイントは以下の7つです。
- フードの見直し
- 安全な住まいづくり
- 快適な睡眠・休息環境
- 体とお口のお手入れ
- 排泄のサポート
- 体調管理と健康チェック
- 飼い主さんのメンタルケア
それぞれ解説していきましょう。
① フードの見直し
シニア期になると活動量が減ってくるため、食事で必要なエネルギーや栄養素も変わってきます。若い頃と同じフードを食べていると、太りやすくなったり内臓に負担がかかったりすることも。



シニア向けのフードには、体に優しい工夫がたくさんつまっています。
- 消化しやすい良質なたんぱく質
- 腎臓や心臓への負担に配慮したミネラルバランス
- 食べやすい形状と柔らかさ
- 食欲が落ちてきた子も食べやすい嗜好性の高さ
健康作りの基本は食事から。まずは「食べにくそうにしていないかな?」「最近残してないかな?」という小さな変化を注意してみましょう
② 安全な住まいづくり
筋力が落ちて足腰が弱くなるると、つまずいたり踏ん張りが効かなくなったりすることが増えます。ちょっとした段差が思わぬケガの原因になることも。
そんなときは、すべり止めマットや段差解消グッズを取り入れることで、ペットが安心して動けるおうちになります。
トイレの場所や数、ベッドの高さなども、いま一度見直してみるとよいでしょう。
体を動かす機会まで奪わない
「ケガをさせたくない」「無理をさせたくない」という思いやりはとても大切です。
でも、先回りしすぎて段差を全てなくしたり、高い場所に上がれないようにすると、運動の機会が減ってしまい、かえって体力の維持には逆効果になることもあります。



不自由そうな姿を見かけてから対応しよう
③ 快適な睡眠・休息環境
シニア期のペットは活動量が減り、一日の多くを寝て過ごすようになります。だからこそ、ベッドや休憩場所の環境づくりは大切です。
ベッドの置き場所は、静かで落ち着けるけれど、「ひとりぼっちにならない場所」を意識すると良いですね。
ベッド選びのポイント
以下のような観点からベッドを選びましょう。
- 出入りしやすい低めのベッド
- 適度な硬さで、体が沈みすぎない
- 寒さ・暑さ対策がしやすい素材
- 好きな場所に移動できる
- 洗える素材
寝たきりや介護が必要になったときは
犬は、足腰が弱ったり、病気で動きにくくなったりすると、寝たきりになることもあります。



猫はもともと体が柔らかく、体重も軽いことから寝たきりになることはあまりありません
そんなときは、以下のような介護グッズを上手に使うことが飼い主さんの負担を減らすためにもおすすめです。
- 防水性・通気性のある介護マットやベッド
- 寝返りをサポートする体位変換用クッション
- 尿、よだれ対策に、吸水シートやタオルの活用
- 床ずれ(褥瘡)予防のクッション
④ 体やお口のお手入れ
猫は毛づくろいや爪とぎで自分の身だしなみを整えています。
しかし、年を取ると体が硬くなったり、興味がなくなったりして、身づくろいが苦手になってきます。
また、犬も猫も、唾液が減ることで自浄作用が落ち、口臭が気になったり、歯肉炎や口内炎にもかかりやすくなるので、オーラルケアも気にしてあげたいところ。



飼い主さんのやさしいサポートがとても大切です。
犬の場合
老犬では、皮膚が乾燥しやすくなったり、寝ている時間が増えたりすることで蒸れやすい部分に皮膚トラブルが起こることがあります。ベッドの環境は気をつけましょう。
また、足腰が弱くなるとお手入れ中の姿勢がつらくなるので、短時間で終わるようにしたり、寝たままでできる工夫もよいでしょう。
猫の場合
ブラシをかけて皮膚の健康を保ち、抜け毛や毛玉の予防をしましょう。
また、爪が伸びたままになると、肉球に刺さったり歩きづらくなったりすることもあるので、定期的に爪切りをしましょう。



お手入れの時間もペットとのスキンシップタイム
⑤ 排泄のサポート
シニア期になると、排泄のタイミングやリズムが少しずつ変わってきます。
- トイレにいく回数、量が変わる
- 寝たままおしっこをしてしまう
- トイレに間に合わずに粗相をする
- トイレの場所がわからなくなってしまう
これは、筋力の低下や神経の反応の鈍り、認知機能の衰えなど、年齢にともなう自然な変化によるものです。



叱ることではなく、ペットからの「助けて」のサイン。
以下のようなポイントを見直してみましょう。
- 出入りしやすい形のトイレにする
- トイレの場所をいつも過ごしている場所のそばに変更する
- 寝たままで排泄するペットには、防水シーツやおむつの活用
排尿や排便の変化は、病気のサインのことも
排尿・排便の異常には、病気が隠れていることも少なくありません。
疑われる病気には以下のようなものがあります。
- 泌尿器系(腎臓、尿管、膀胱、尿道)の病気
- 消化器系の病気
- ホルモンの病気
- 子宮、前立腺など生殖器系の病気
- 認知症
- ストレス
以下のサインは見逃さないように注意しましょう。
- 尿や便の回数・色・臭い・形状の変化
- トイレの様子がいつもと違う(踏ん張るが出ない、痛がって鳴く、時間が長いなど)
- トイレ外での排泄が急に増えた
- 食欲や元気も一緒に落ちている
トイレの悩みは、飼い主さんにとっても負担が大きく感じられるかもしれません。



お互いが楽になる方法を見つけていくことで、気持ちが軽くなります。
⑥ 体調管理と健康チェック
シニア期になると、腎臓病、心臓病、歯周病などの慢性疾患にかかりやすくなります。
シニア期のペットがかかりやすい病気
年齢とともに増えてくる病気には以下のようなものがあります
- 慢性腎臓病(特に猫に多い)
- 心臓病(小型犬に多い)
- 関節炎やヘルニア
- 認知症(特に犬で夜鳴き・徘徊・トイレの失敗など)
- 腫瘍
- 口腔内トラブル(歯周病や口臭)
どれも早めに気づいて対処すれば進行をゆるやかにできたり、負担を減らすことができる病気です。
動物病院との付き合い方
シニア期を迎えたら、動物病院は「病気やワクチンの時に行く」だけでなく「定期的に健康状態をチェックしてもらう場所」として付き合っていくのがおすすめです。



半年に1回の健康診断でがおすすめ
気軽に相談できる病院があると、飼い主さん自身の安心にもつながりますよ。
⑦ 飼い主さんのメンタルケア
我が子のように思っていたペットの老いた姿を見るのは、寂しさや辛さを感じることもあるでしょう。そう遠くないうちに必ず来る別れを思うと、心がふと沈んでしまうこともあるかもしれません。
ペットの介護をしていると、「この子のためにがんばらなくちゃ」、「でも、正直しんどい…」という相反する2つの気持ちを抱えてしまうのはとても自然なことです。



飼い主さんの心と体も大事にしてください
活用できるサポートもあります
最近は、飼い主さんを支えるサービスも少しずつ広がってきています。
- 老犬・老猫ホーム:介護が必要になった子のための安心な住まい
- デイケアサービス、一時預かり:数時間〜数日預かってくれる場所もあります
- 訪問介護(ペットシッター・獣医訪問):おうちでケアを受けられるサービス
- オンライン相談:老いや介護の疑問、不安な気持ちや悲しみを、信頼できる人や専門家に話す
こうしたサービスを利用することは「手抜き」ではありません。介護は終わりが見えないため、できることを無理なく続けることが何よりも大切です。
「自分自身と大切な家族を守るための選択肢のひとつ」としてサービスの利用を前向きに捉えることが、飼い主さんの心の安定にもつながります。
まとめ


シニア期を迎えたペットのケアに必要な7つのポイントを解説しました。
- フードの見直し:シニア向けフードで楽しく健康作りを
- 安全な住まいづくり:不自由そうな様子がみられたら階段やスロープの設置を
- 睡眠・休息環境:寝る時間が増えるので、ベッドの位置や布団の硬さなどを見直す
- 体とお口のお手入れ:スキンシップを取りながら体やお口のケアを
- 排泄のサポート:トイレの見直し、排泄物の様子で健康チェックを
- 体調管理と健康チェック:半年に1回は動物病院で健康診断を
- 飼い主さんのメンタルケア:ご自身の心と体を楽にするサポートの活用を
シニア期のペットは、かつてのような無邪気さや元気は少しずつ影をひそめていくかもしれません。でも今は、ともに歳を重ねてきたからこそ築けた、静かで深いつながりがあるはずです。
あなたの頑張りや思いやりは、きっとまっすぐに伝わっています。どうかご自身の心と体の声にも、やさしく耳を傾けてあげてくださいね。